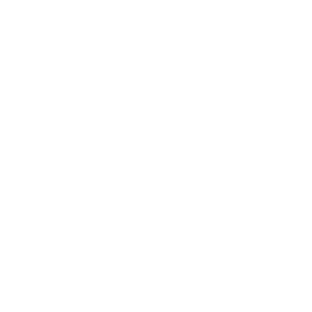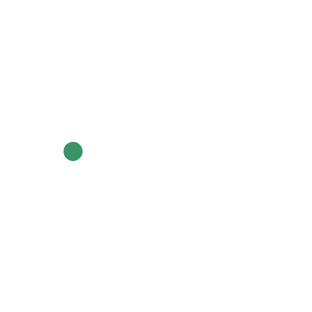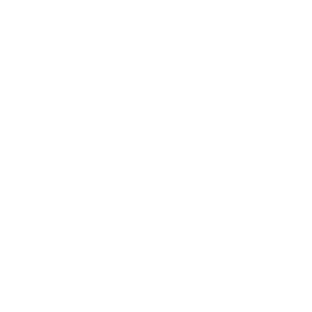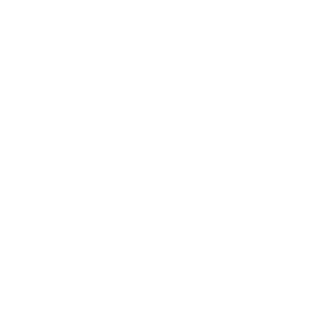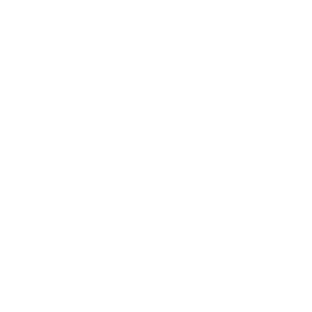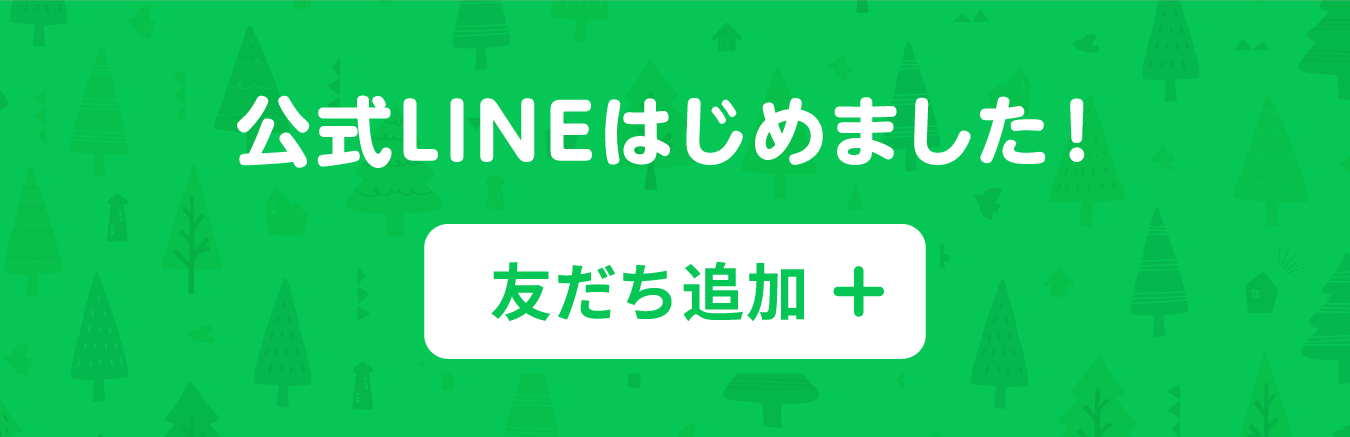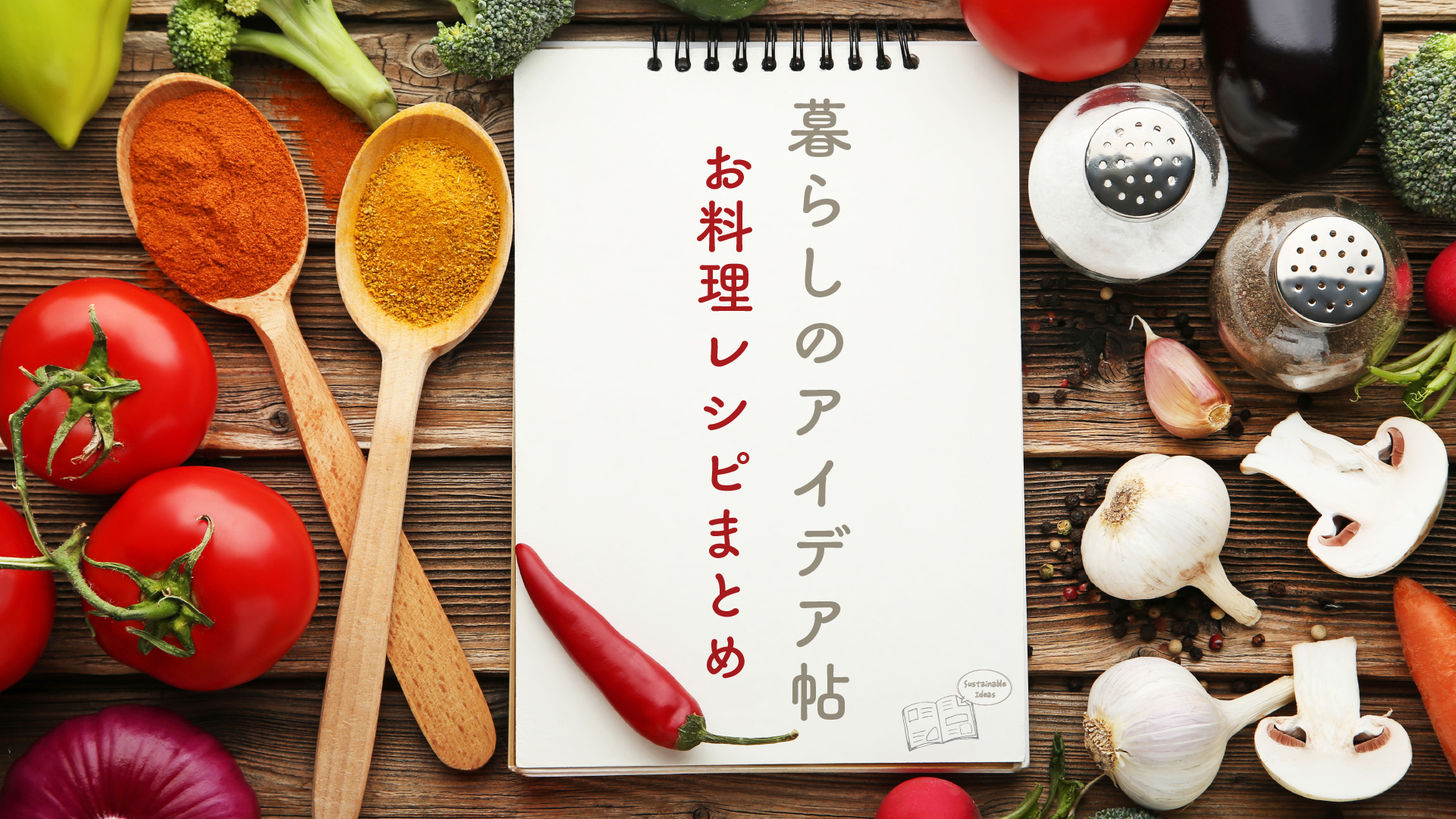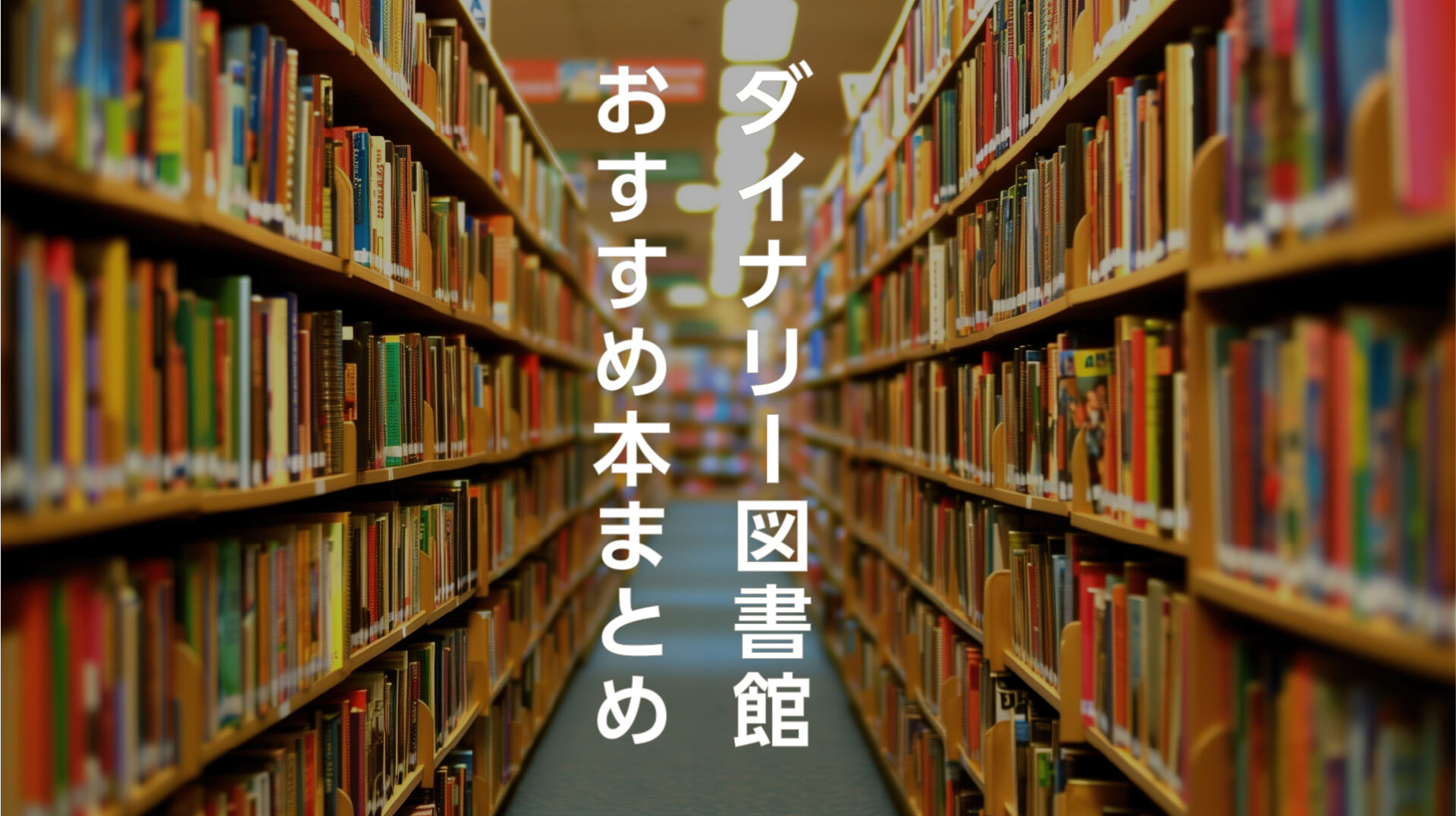おもちゃのリサイクルとは

おもちゃのリサイクルは、文字通りおもちゃをリサイクルしてサーキュラーエコノミーの構築を目指す取り組みです。たとえば、使わなくなったおもちゃを回収し、素材ごとに分別して再資源化したり、状態の良いものはクリーニングして寄付や再販売に回したりすることで、廃棄物の削減と資源の有効活用を図ります。リサイクルして作られたおもちゃそのものを指して「リサイクルおもちゃ」と呼ぶこともあります。
おもちゃのリサイクル方法は、多岐に渡ります。イメージしやすい「修理・回収・再利用」など代表的な手段から、廃材を使ったおもちゃづくりなど多様な施策があるのでチェックしてみましょう。おもちゃのリサイクルは、限りある資源を有効活用し、新たな製品の製造に必要な資源を節約することにつながります。
\サーキュラーエコノミーとは?/
なぜおもちゃのリサイクルが必要なのか?

おもちゃは流行・年齢・発育に応じて頻繁に買い替えられるものであり「大量生産・大量消費」されることが多いです。「まだまだ使えるのに捨てられる」「数ヶ月から数年で使われなくなってしまって勿体ない」という現象も起きており、故障もしていないおもちゃが大量のごみになることは少なくありません。 また、多くのおもちゃはプラスチック・電池・金属など複数の素材を使っていて、分別やリサイクルが難しい構造になっています。分別が難しいからこそ丸ごと焼却されるなど、地球温暖化・大気汚染・資源の無駄につながることも多いのが問題視されるようになりました。
おもちゃも貴重な資源であり、短期間で捨てていては、限りある資源がどんどん無駄になってしまいます。 国も温暖化対策の一環として二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を2050年までに実質的にゼロにする目標を掲げており(※)、「使い捨て前提の社会」から「循環型社会」への移行が求められるようになりました。
現在ではおもちゃの回収・再利用だけでなく、リサイクル素材をつかったエコなおもちゃの生産や譲渡による社会貢献など、幅広い活動が始まっています。おもちゃのリサイクルに対する注目も年々増加しており、おもちゃの使い方を見直すきっかけとなっていくでしょう。
(※)参考:NHK|“温室効果ガス 2013年度比60%削減” 国連に目標提出
(※)参考:外務省|日本の排出削減目標 - 気候変動
おもちゃのリサイクル方法

ここでは、おもちゃの代表的なリサイクル方法を例にあげて詳しく解説します。それぞれの分野で具体的にどのような取り組みが行われているのか、確認してみましょう。
修理による再利用
修理による再利用とは、壊れたり使えなくなったりしたおもちゃを修理し、再び使える状態にして再利用する方法です。廃棄されるおもちゃを減らす手法であり、廃棄物の削減やおもちゃを焼却処分するときのエネルギー節約・二酸化炭素の排出低減など、多くの効果が期待できます。例えば、以下のような取り組みが挙げられます。
- 「おもちゃ病院」「おもちゃドクター」など地域密着での修理
- メーカー公式による部品交換などの修理
- 修理ワークショップなど修理技術の伝達・指導
- リサイクルショップによる修理・クリーニング
- 「ぬいぐるみクリーニング」など綺麗に長持ちさせるサービス
また、子どもたちに対して「お気に入りのおもちゃを大切にする心」や「修理して長く使う大切さ」を教えることにもつながります。おもちゃをはじめとする様々なアイテムの物持ちをよくしたいときや、保育園・幼稚園・児童館などでおもちゃを長く使い続けたいときにも役立ちます。
譲渡・中古販売による再利用
譲渡・中古販売による再利用とは、まだ使えるおもちゃを必要としている人へ譲ったり、新品の価格よりも安価に買い取ってもらうことで、おもちゃの寿命を最大限に活かす方法です。近年、廃棄物の削減だけでなく社会貢献にもつながる手法として注目を集めるようになりました。例えば、以下のような取り組みが挙げられます。
- 児童養護施設や小児病棟への寄付
- フリマアプリを使った譲渡
- オンラインマッチングサイトでの譲渡
- フリーマーケットでの譲渡・販売
- リサイクルショップでの買取・販売
地域密着で実施されているフリーマーケットから、フリマアプリやオークションサイトを使った譲渡や販売など、近年は再利用につながる方法も多様化しています。「お金がなくて新しいおもちゃを買えない」という家庭の支援にもつながる、一石二鳥の取り組みといえるでしょう。
素材の再利用
素材の再利用とは、遊ばなくなったおもちゃや壊れてしまったおもちゃからまだ使える素材を取り出し、新たな製品の原料にする方法です。 例えばプラスチック製おもちゃの場合、一度粉砕・溶解され、新たなプラスチック製品の原料として再利用されることが多いです。その他にも、木製のおもちゃを木材チップに加工したり、金属製のおもちゃを溶解して別の商品に作り変えたりすることもあります。素材の再利用につながる取り組みは以下のようなものが挙げられます。
- おもちゃ屋の不要おもちゃ回収ボックスの利用
- 自治体や企業が運営するプラスチック・木材・金属などの回収サービスの利用
おもちゃメーカーが自社製品の回収・リサイクルシステムを構築していることもあれば、メーカー問わず幅広く回収してから再利用を検討することもあります。製品の開発サイクル全体で環境負荷を低減する取り組みであり、循環型社会の実現に貢献します。
廃材を使ったおもちゃづくり
廃材を使ったおもちゃづくりとは、廃材の形や特性を活かしておもちゃを作る方法です。例えば、トイレットペーパーの芯や牛乳パックを使って自宅や保育園・幼稚園で工作することも「廃材を使ったおもちゃづくり」に該当します。その他、企業が主導する廃材ワークショップなども代表的な施策です。
- 廃材おもちゃを使ったアップサイクル
- 廃材を使ったおもちゃづくりのワークショップ
- 空き箱を使った工作
コストをかけずに簡単にできる工作も多く、子どもの創造性を育みながら環境問題への意識も高められます。壊れにくい丈夫なおもちゃになるよう工夫を凝らすなど、楽しめるポイントも多いです。
\使わない絵本カバーをパズルに!/
おもちゃをリサイクルするメリット

ここでは、おもちゃをリサイクルするメリットを解説します。なぜ近年おもちゃのリサイクルに注目が集まっているのか、チェックしてみましょう。
廃棄物を削減できる
おもちゃをリサイクルすることは、廃棄物の削減につながります。
現代社会では大量生産・大量消費をされることが多くなっていて、おもちゃも例外ではありません。プラスチック製のおもちゃを中心に多くのおもちゃが短期間で廃棄され、埋立地のひっ迫や焼却により大量の二酸化炭素が排出され環境汚染を引き起こしています。
一度壊れてしまっても修理しながら使い続けたり、年齢に合わなくなったおもちゃを年下の子どもに譲ったりすることで、廃棄されるおもちゃはグッと減らすことが可能です。おもちゃのリサイクルは、廃棄物削減を通じて持続可能な社会の実現に貢献する、重要な取り組みといえるでしょう。
資源を有効活用できる
捨てるしかなくなったおもちゃをそのまま焼却処分するのではなく、一度素材に戻して再利用することで資源を有効活用できるのがメリットです。おもちゃに使われているプラスチック・金属・木材などの資源を廃棄せずに再利用すれば、新しく使われる素材を削減できます。結果として、新たな資源の採掘や生産に伴う環境負荷を低減し、資源の枯渇を防ぎやすくなるでしょう。
限りある資源を大切に使う取り組みでもあるため、持続可能な社会づくりに貢献します。資源を循環させることにもつながり、メリットの多い取り組みといえます。
大気汚染を抑制できる
おもちゃをリサイクルすることで、焼却時のダイオキシンや窒素酸化物など、有害物質の排出を抑制して大気汚染を抑制できます。
窒素酸化物の年間排出量は約45万トンに達しており、その一部は廃棄物の焼却によるものとされています。リサイクルによって焼却処分を減らすことで、有害物質の排出を抑制し、大気汚染の防止や地球温暖化対策につながります。
マイクロプラスチックを削減できる
マイクロプラスチックとは、直径5ミリ以下の微小なプラスチック片のことを指す言葉です。ペットボトル・レジ袋・食品容器などの破片や、おもちゃ・釣り具・漁網などの海洋流出ごみにマイクロプラスチックが含まれており、小さな魚や鳥などがマイクロプラスチックをエサと間違えて食べてしまう現象が確認されています。
目に見えないほど細かいマイクロプラスチックも多く、海・川・土などあらゆる場所にマイクロプラスチックが存在しています。一度海や山と混ざってしまったマイクロプラスチックは手で取り除くのが難しいからこそ、使わなくなったプラスチック製品は適切に処分・リサイクルすることが求められます。
おもちゃをリサイクルすることは、マイクロプラスチックの削減に役立ちます。廃棄物として環境中に出るマイクロプラスチック量を減らせる他、焼却や埋立を回避することでマイクロプラスチック化を防ぐことも可能です。
おもちゃのリユースであれば、そもそもおもちゃがゴミにならないため、更に効果的でしょう。リサイクルにより有害物質の排出抑制など環境汚染対策ができれば、環境への負担を軽減することにつながります。
環境教育につながる
リサイクルおもちゃは、子どもたちに環境問題への意識を高めてもらうための教材としても使えます。「このリサイクルおもちゃは元々どんなものだったでしょう?」と簡単なクイズを出したり、おもちゃが生まれ変わる工程を工場見学やレポートで学んだりすることも可能です。
結果、おもちゃの廃棄が環境に与える影響や資源の枯渇への危険性について考えるきっかけを与えられるでしょう。環境問題への関心を高めることにもつながり、持続可能な社会の実現に向けた具体的な行動が可能です。
寄付による社会貢献ができる
おもちゃをリサイクルする取り組みは単に廃棄物を減らすだけでなく、寄付を通じて社会貢献することにもつながります。おもちゃは、子どもたちの健全な成長に欠かせません。寄付されたおもちゃは、経済的な理由で新しいおもちゃを買うことが難しい子どもたちに遊びと学びの機会を与えることになるでしょう。子どもたちの心のケアができる他、教育や遊びの機会も増やせるので、メリットも多いです。
寄付する前に、おもちゃが安全に使用できる状態であることを確認しましょう。破損がないか、年齢・月齢に合わせて誤飲などのリスクがない状態になっているかチェックし、ニーズに合うおもちゃを寄付することが大切です。
企業や団体によるおもちゃの3R事例

ここでは、リサイクルだけじゃないおもちゃの3R(リユース・リデュース・リサイクル)に関する取り組み事例を解説します。おもちゃの3Rに関する取り組みは幅広く、企業が主導するものから、市区町村・NPO法人・NGO主導のものまでさまざまです。以下でチェックし、身近な取り組みも探してみましょう。
タカラトミー|エコトイ事業
大手おもちゃメーカーであるタカラトミーでは、おもちゃを通じて子どもたちの環境意識を育むため「エコトイ事業」を始めています。以下の9つの基準のうち、いずれか1つ以上を満たしたおもちゃを「エコトイ」として認定しているので購入時の参考にしてみましょう。
- 省資源なおもちゃ
- 再生材料を使用したおもちゃ
- 省エネルギーなおもちゃ
- 省エネルギーおよび廃棄物削減ができるおもちゃ
- 省資源・資源の有効活用ができるおもちゃ
- カプセルも製品として遊べるおもちゃ
- 長期使用の促進につながるおもちゃ
- 成長に合わせて形を変えられるおもちゃ
- 環境配慮の心を育むおもちゃ
「エコトイ」には、おもちゃのリサイクルだけでなく環境配慮の心を育むおもちゃなども含まれています。環境問題全般についての取り組み施策であり、パッケージ自体を遊びに活用できるデザインやガチャガチャのカプセルも製品として遊べるおもちゃなど、独自性の高い取り組みも見られます。 また、長く使える丈夫な製品設計や修理や部品交換が容易な設計などにも配慮されていて、おもちゃメーカーとしての企業努力が伺えます。
一般社団法人日本おもちゃ病院協会|無料おもちゃ修理ボランティア
一般社団法人日本おもちゃ病院協会では、無料でおもちゃ修理ボランティア活動をしています。具体的な活動として、全国各地に約700箇所ある「おもちゃ病院」にて、原則無料でおもちゃの修理を行っているのが特徴です。おもちゃドクターと呼ばれるボランティアの方々が専門的な知識と技術で修理を担当してくれるので、安心して任せられます。
また、児童館やショッピングモールでの「出張おもちゃ病院」も定期的に開催しているのがポイント。おもちゃ病院の活動を広く知ってもらうための広報活動や、新たな病院の設立支援なども行っています。
東村山市|おもちゃリユースプロジェクト
東村山市が実施している「おもちゃリユースプロジェクト」は、家庭で不要になったおもちゃを回収し、カンボジアなど海外で再利用することを目的とした取り組みです。廃棄物の削減と資源の有効活用を目指し、循環型社会の実現に貢献することを目的としています。 市役所の他、スポーツセンターや地域の家電量販店・リサイクルショップでの回収も実施されており、市民が手軽に寄付できるようになっているのがポイントです。寄付に出向く面倒さや手間を省き、手軽に協力してもらえる仕組みづくりができました。
また、ライフスタイルのエコシフトをお手伝いする企業・株式会社エコランドが「おもちゃリユースプロジェクト」に協力しています。官民が協力するスタイルのおもちゃリサイクルであり、全国で同様のプロジェクトが発足することが期待されます。
NPO法人グッドライフ|保育園や児童館への寄付
NPO法人グッドライフは、国内外で不用品の寄付活動を行っている団体です。特に、保育園や児童館への寄付を通じて、子どもたちの成長を支援する活動に力を入れています。子どもたちの成長に欠かせないおもちゃや絵本を積極的に回収している他、有事の際は小児病棟や被災地への寄付も行っています。
また、寄付先は国内の保育園や児童館だけでなく、海外の教育機関や難民キャンプなど多岐にわたるのも特徴です。発展途上国の子どもたちに教育用品や生活用品を届ける活動など、多岐に渡る支援活動を始めました。環境問題対策になるリサイクルおもちゃの他、社会貢献活動にも積極的です。
マクドナルド|ハッピーセットのおもちゃリサイクル
マクドナルドの「ハッピーセットのおもちゃリサイクル」は、子どもたちに人気のハッピーセットについてきたおもちゃを回収し、リサイクルする取り組みです。全国のマクドナルド店舗に回収ボックスが設置されているので、実際に目にしたことのある方も多いのではないでしょうか。消費者参加型の活動であり、子どもが自分のおもちゃを自分で回収ボックスに入れることで、リサイクルへの意識を高めてもらう教育活動としても機能しています。
回収ボックスに入れられたおもちゃはリサイクルされ、マクドナルドの店舗で使用される緑色の食品トレイに生まれ変わります。その他、家電製品等の素材としてリサイクルされることも多く、プラスチックの廃棄量削減が可能です。
三菱電機×カワダ|廃プラスチック再利用に関する共同研究
三菱電機株式会社と株式会社カワダのコラボレーションにより、廃プラスチック再利用に関する共同研究が始まっています。家庭などから廃棄されるプラスチックの回収・リサイクルの推進が目的であり、2024年には「東京おもちゃショー」にも出展しました。家電由来のリサイクル材から試作したおもちゃなどオリジナリティあふれる展示が多く、環境に配慮した技術開発と業界を超えたリサイクルプロセスの確立に貢献しています。
また、本プロジェクトでは、三菱電機グループの家電リサイクル事業で培われたプラスチック高度選別技術と、カワダが保有するサステナブルな取り組みの実績や知見とがコラボレーションしています。1社だけではできなくても、複数の会社が協力しあうことで新たな施策が生まれるかもしれません。
マテル・インターナショナル|海洋プラスチックを使ったバービー人形
マテル・インターナショナルは、世界的に有名なファッションドール「バービー」を通じて、環境問題への意識を高める取り組みを行っています。代表的な取り組みとして、海洋プラスチックをリサイクルした素材を使用した「バービー うみとともだち」シリーズをリリースしました。
人形の素材の90%に海洋プラスチックのリサイクル素材を使用しているのが特徴で、ドレスやアクセサリーにもリサイクル素材を使っています。海をテーマにしたデザインになっており、子どもたちが海洋環境問題に関心を持つきっかけとしても使えるでしょう。
\何を作るかは子供たち次第!廃材を使ったワークショップ/
おもちゃのリサイクルに興味がある人におすすめの活動

おもちゃのリサイクルに興味がある人は、身の回りで手軽にできるところから協力してみてはいかがでしょうか。例えば、以下は個人でも行動に移しやすく、おもちゃのリサイクルと関連した消費行動に繋がります。
リサイクルに積極的なおもちゃメーカーの商品を購入する
リサイクルに積極的なおもちゃメーカーの商品を購入することで、環境保護に貢献する方法があります。
タカラトミーでは、「100ねんあそぼ。」をコンセプトに、おもちゃの企画・開発・製造・販売・遊び・廃棄など全ての段階で環境への配慮を組み込んだ「エコトイ」を展開しています。セガトイズもおもちゃの下取りサービス「セガトイズエコプロジェクト」を実施しており、不要になったおもちゃを回収してリサイクルしているのでチェックしてみましょう。
また、おもちゃの素材やパッケージを確認し、リサイクル素材が使われているか、環境に配慮した素材が使われているかを確認して購入先を検討する方法もあります。おもちゃの耐久性や修理の可否、子ども向けの環境イベントの開催可否などをチェックして、信頼できる「お気に入りのおもちゃメーカー」を探してみるのもおすすめです。
FSC認証商品など素材に配慮したおもちゃを購入する
「FSC認証」とは、適切に管理された森林から伐採された木材を使い、環境や地域社会に配慮した製品であることを証明する認証です。おもちゃ以外の認証商品も多いですが、木を使うおもちゃがほしいときはチェックしてみましょう。
他にも、1,000種類以上の有害化学物質を対象とする厳しい分析試験にクリアした製品のみに認められる「エコテックス認証」を意識するなど、工夫することも可能です。廃棄時の処理や代替エネルギーを使った製造を意識しているおもちゃメーカーが該当することもあるので、ぜひご確認ください。
リサイクルショップやフリーマーケットを活用する
リサイクルショップやフリーマーケットを活用することは、おもちゃのリユースを促進し、廃棄物の削減に貢献する手段のひとつです。
リサイクルショップであれば、専門のスタッフが査定を行い、おもちゃの状態や人気度に応じて買い取ってくれるので金銭的なメリットもあります。比較的状態の良いおもちゃや人気のあるおもちゃは高値で売れる可能性があり、かつリサイクルにも貢献できるので一石二鳥です。
フリーマーケットの場合、自分で価格を設定し、買い手と直接交渉しながらおもちゃを販売する楽しさがあります。フリーマーケットアプリやオークションサイトでの販売もできるので、検討してみましょう。
修理・清掃をしておもちゃを長く使う
少し調子が悪くなったおもちゃでも簡単に捨てず、修理・清掃をして長く使うことを意識してみましょう。例えば、ゲームコントローラーのスティックやラバークリップなどは、単品で部品のみを購入して交換できることがあります。その他、手軽に交換できる部品であれば交換を検討してもよいでしょう。
とはいえ、基盤のある電子おもちゃを家庭で自己修理することは危険です。家庭向けの修理方法が公開されていない商品では、メーカー修理やおもちゃ病院を活用するなど工夫し、安心・安全に使えるよう対策しておきましょう。
まとめ
本記事では、おもちゃのリサイクルの取り組み事例として、企業自治体など様々な団体による活動を紹介しました。おもちゃのリサイクルは、おもちゃの廃棄による環境負荷を低減し、資源の有効活用を促進することで持続可能な循環型社会の構築に貢献しています。
おもちゃのリサイクルに関する取り組みはまだ発展途上であり、今後の活動の広がりが期待されています。10年〜20年先の未来を生きていく子供達のためにも、おもちゃという子供達にとって身近な部分から親子で環境問題について考えはじめてみてはいかがでしょうか?
【参考】
NHK|“温室効果ガス 2013年度比60%削減” 国連に目標提出
外務省|日本の排出削減目標 - 気候変動
株式会社タカラトミー|エコトイ
日本おもちゃ病院協会|活動内容
東村山市|「おもちゃリユースプロジェクト」のご紹介【東村山市わたしたちのSDGsパートナー認定企業協働事業】
NPO法人グッドライフ|おもちゃを寄付したい方。NPO法人が保育園・放課後児童館・海外の孤児院へ届けます。
日本マクドナルドホールディングス株式会社|おもちゃリサイクル
三菱電機株式会社・株式会社カワダ|三菱電機とカワダが家電や玩具の廃プラスチック再利用に向けた共同研究を開始
マテル・インターナショナル株式会社|バービー史上初!海洋プラスチック再生素材を使用した地球にやさしいシリーズがデビュー!「バービー うみとともだち(Barbie Loves the OceanTM)」