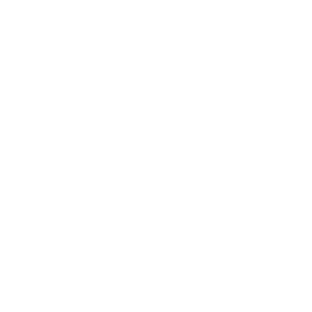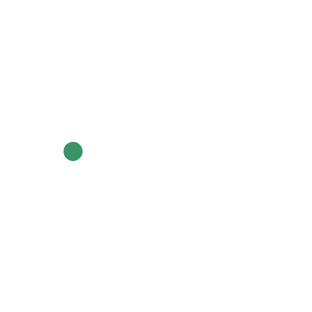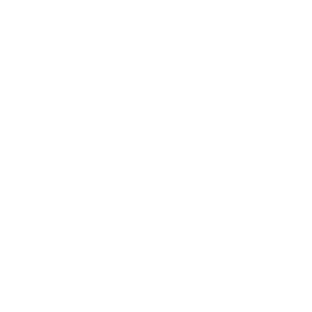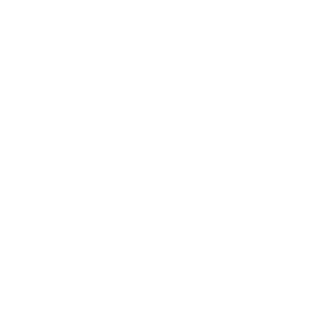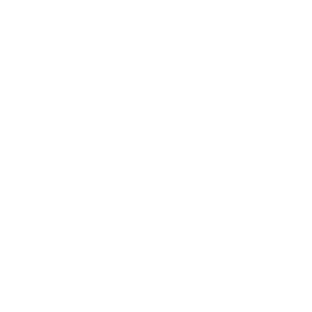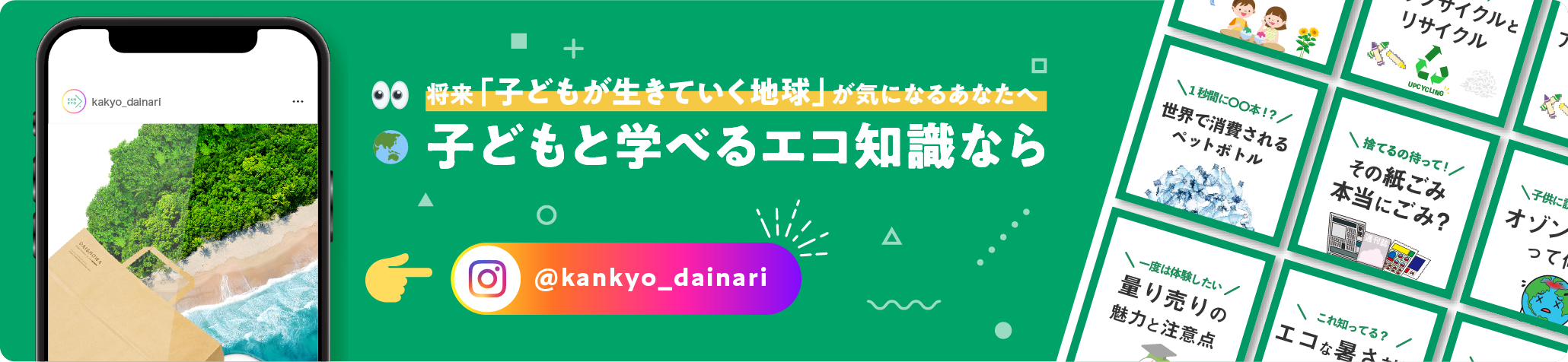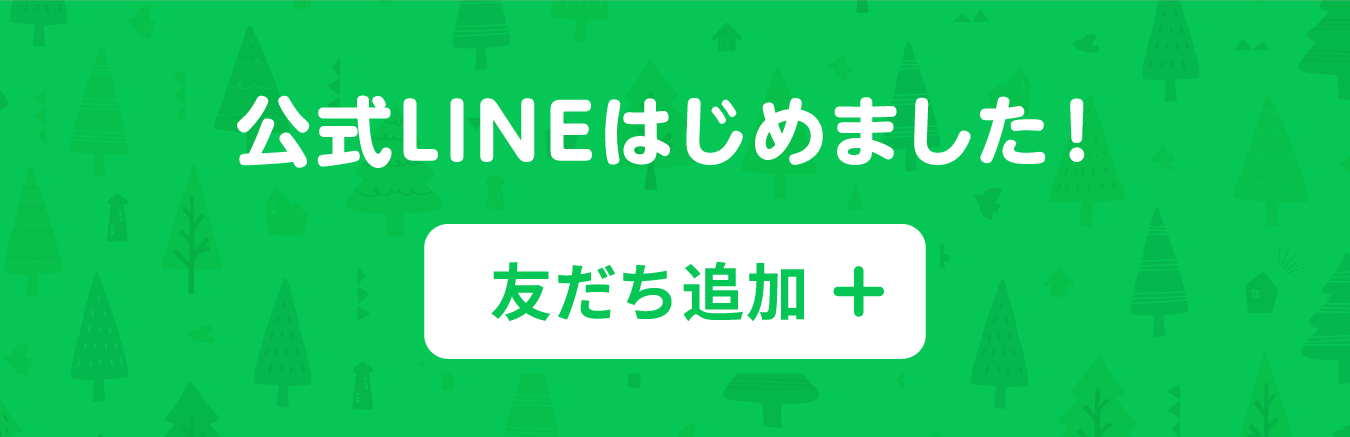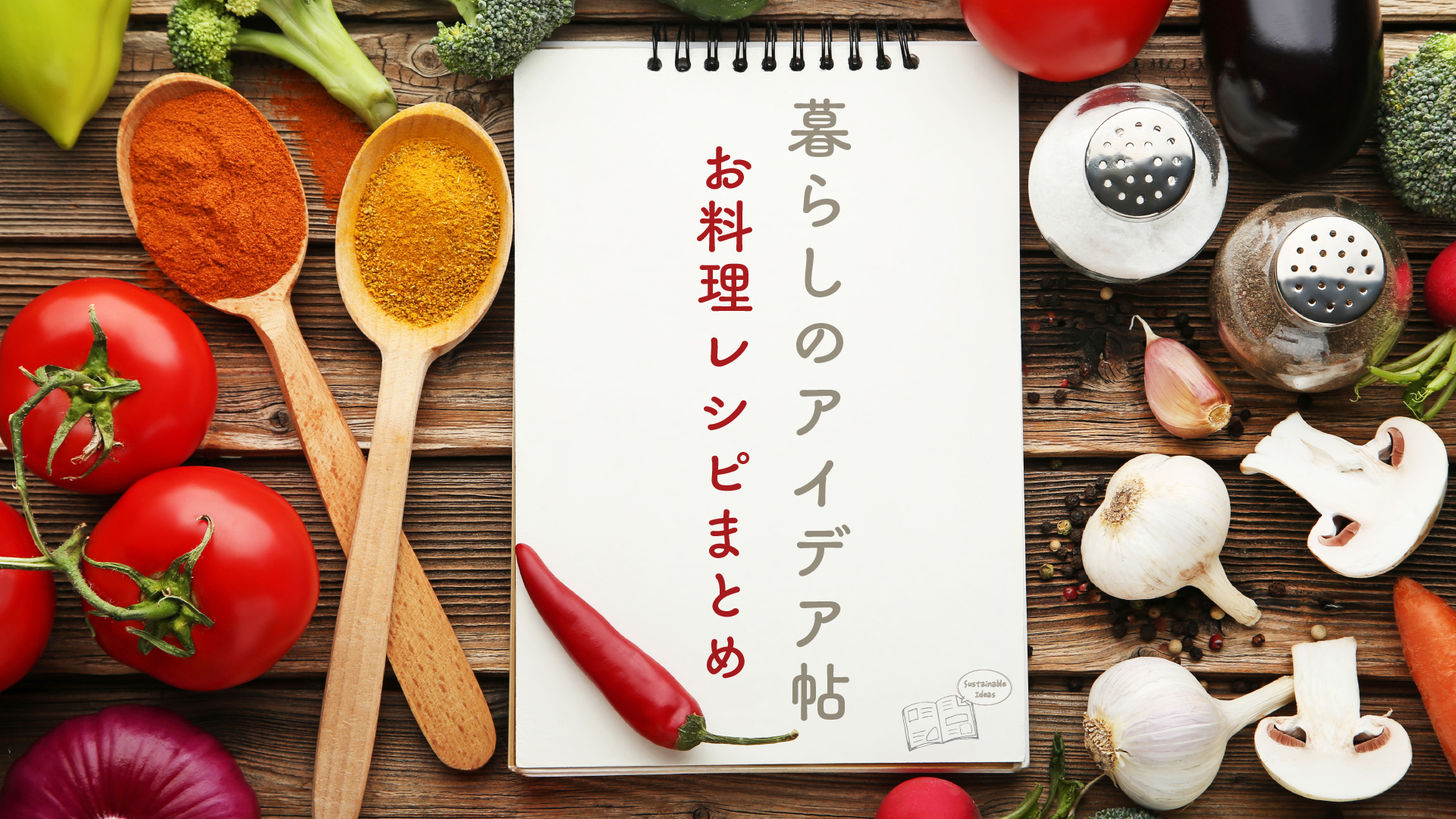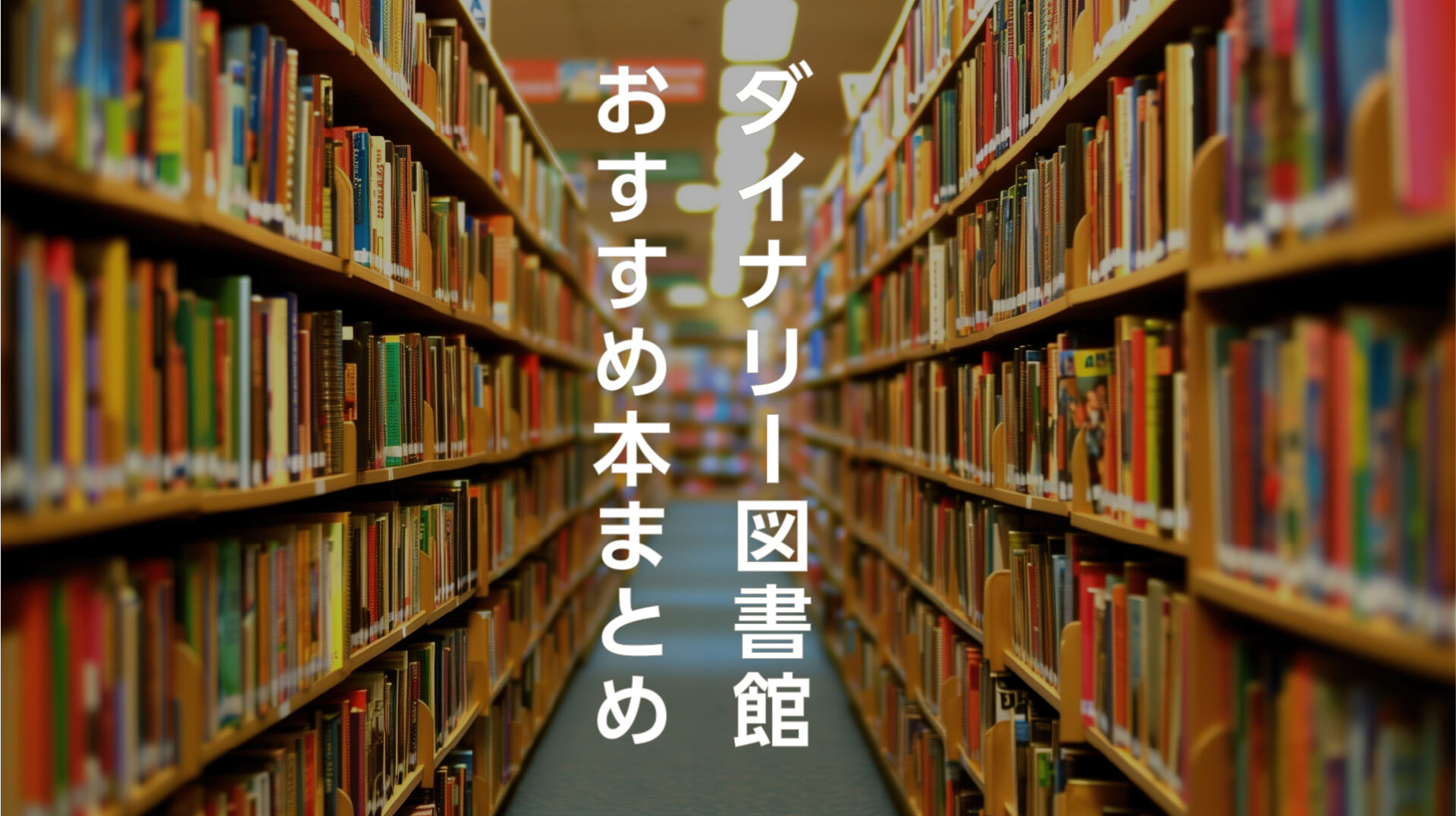木を収穫する
主伐エリア
取材当日は、主伐(しゅばつ:木をまとめて伐る作業)の予定が組まれたエリアでチェーンソーを使って作業をする方々が。

▲伐採のスケジュールを決める森林施業プランナーと作業をするフォレストワーカーの方々
「伐採」と聞くと、「森が壊されてしまうのでは?」と不安に思う方も多いかもしれません。しかし、主伐や間伐といった“伐採”は、果樹園で果実を収穫するのと同じように、森を健やかに育てていくための大切な工程です。

▲チェーンソーを入れ、計画した方向に木を倒す。チェーンソー、倒れた木の扱いなど林業従事者の作業には危険が多く伴う。

▲重厚な音とともにゆっくりと倒れていく約20Mの大木は大迫力
▲動画で見る
計画的に育てられ、50〜60年成長し収穫期を迎えた木は、適切なタイミングで「収穫(伐採)」することで、森全体の健康を保ち、次の世代の木々がしっかりと成長できる環境をつくります。実際、成長がピークを過ぎた木は、若い木と比べて二酸化炭素の吸収量が大きく低下するというデータもあります。だからこそ、伐採は森や地球のためになる“持続可能な循環”の一部なのです。

▲異なるサイズのチェーンソーを持たせていただき「この重さを自在に操るのか」と驚愕するカンキョーダイナリースタッフ。

▲主伐のあとに残った切り株や、規格外で商品にならないために残された木は長い時間をかけ自然に還っていく。
積み込みと運搬
伐採された丸太はその場で終わりではありません。丸太を掴む林業専用機械「グラップル」で伐出作業し、トラックへの積み込みや運搬といった次の工程へとスムーズに移り、やがて建材や製品など、私たちの生活に欠かせないかたちへと生まれ変わっていきます。


伐採された丸太は製材所に運ばれ、用途に応じて柱材などに加工されます。真っすぐな部分は住宅用の柱や梁に、節の多い部分や細い端材はチップやペレットに加工され、紙の原料やバイオマス燃料などに活用されます。一本の木を無駄なく使い切ることで、資源循環型の森づくりが実現されています。

▲加工について説明してくださっているプランナーさん。丸太の中心の数字は直径(センチ)を表している。
\スタッフが探訪した様子をレポート!/